
2023/7/3
【ハラスメント】あなたのセクハラ認識度合いは?
ハラスメントブログ

2023/6/19
【心】感情が人生の成否「成功と失敗」の原因 ♪脳はだまされやすい♪
ブログ心・メンタルヘルス関係

2023/6/12
【心】墓碑銘に刻みたい言葉はなに?
ブログ心・メンタルヘルス関係
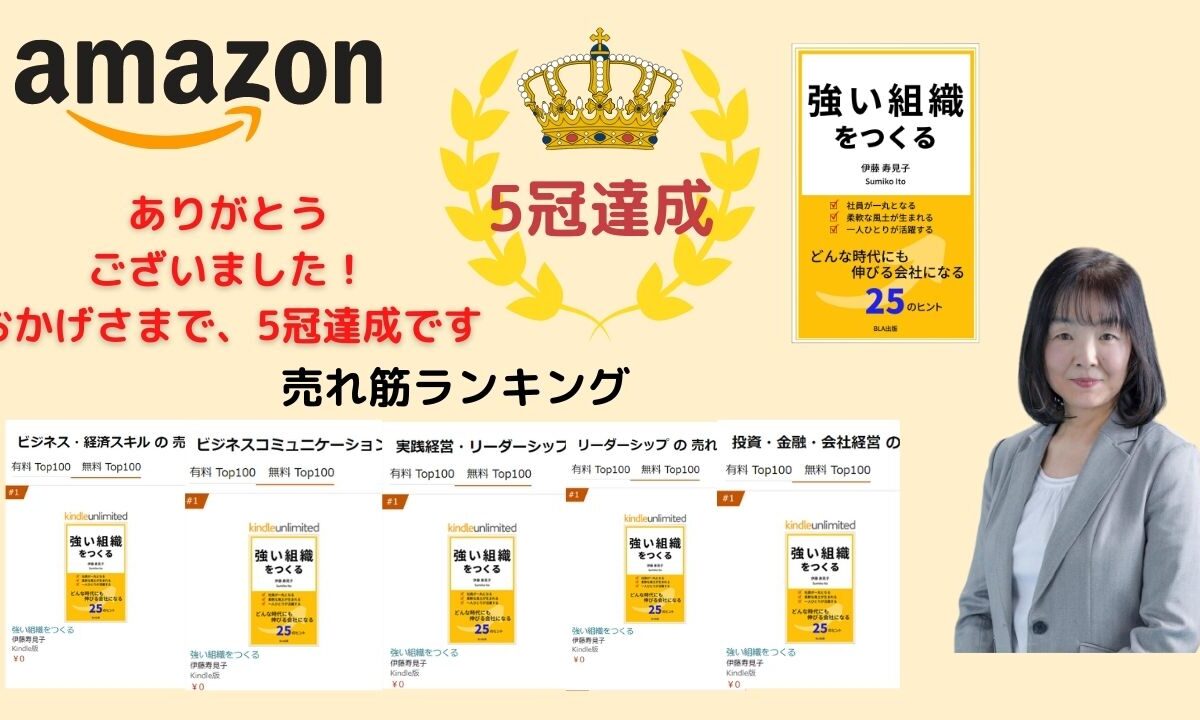
2022/12/12
褒められ・認められ・感謝され、メンバーが成長を実感できる組織は強い!
強い組織をつくる 実践25のヒント便り

2022/12/5
問題発生は「身から出たさび」、人ではなく「仕組みを憎もう!」
強い組織をつくる 実践25のヒント便り
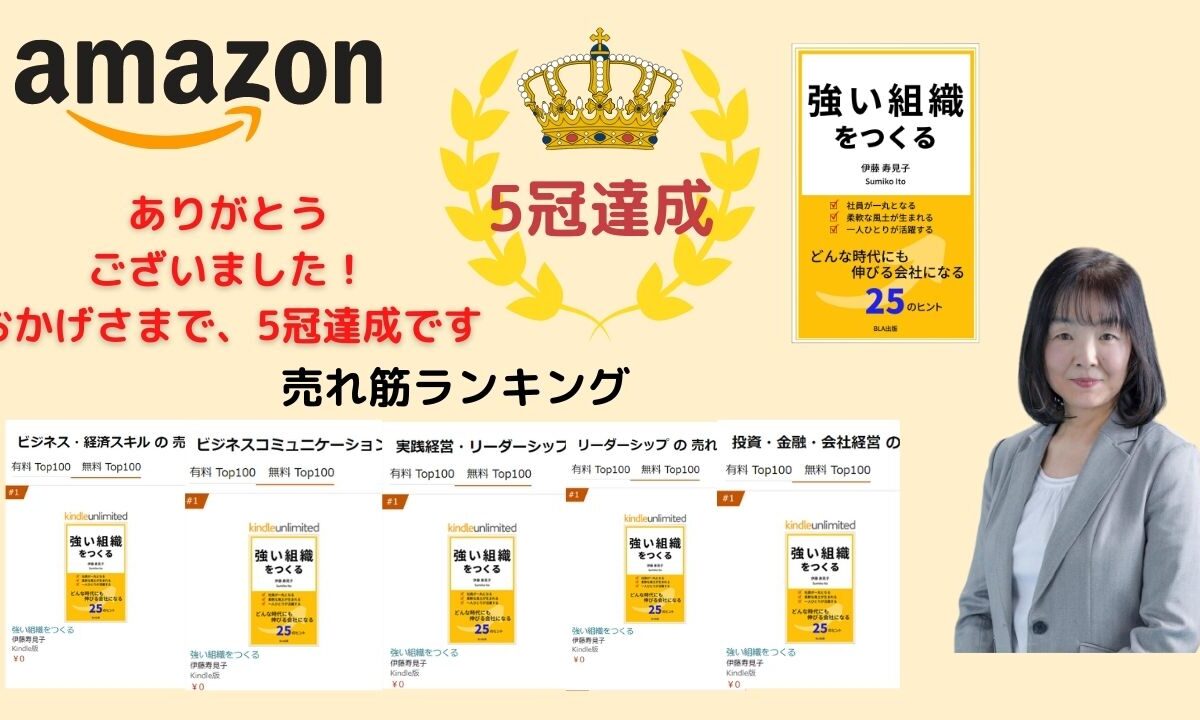
2022/11/28
部下を大きく育てる7つのポイント
強い組織をつくる 実践25のヒント便り
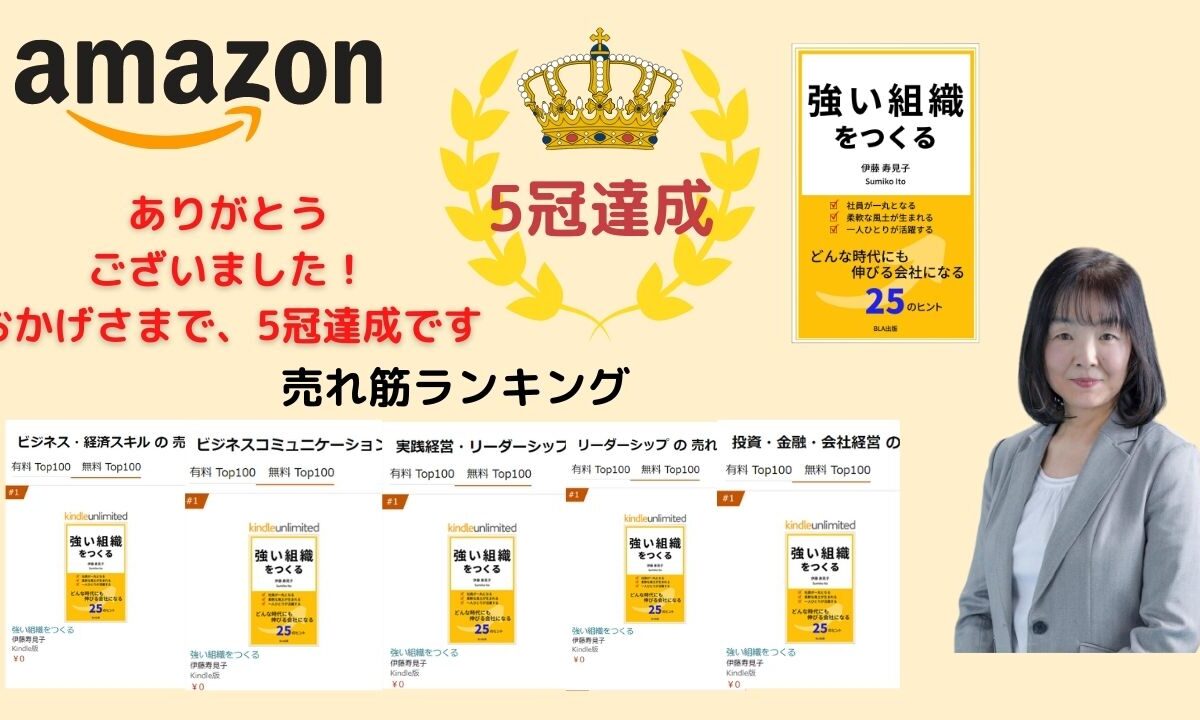
2022/11/21
部下との信頼関係は、愛と思いやりで深くなる
強い組織をつくる 実践25のヒント便り
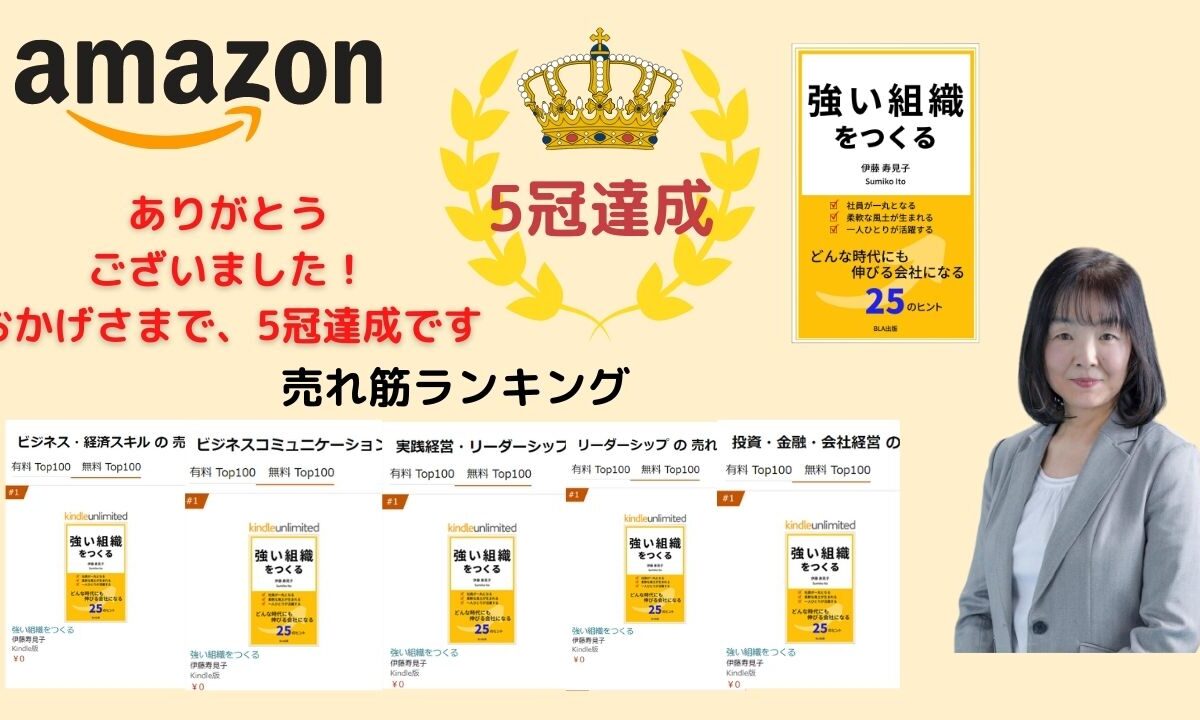
2022/11/14
部下の可能性を広げる「良い質問」は、パワフル!
強い組織をつくる 実践25のヒント便り
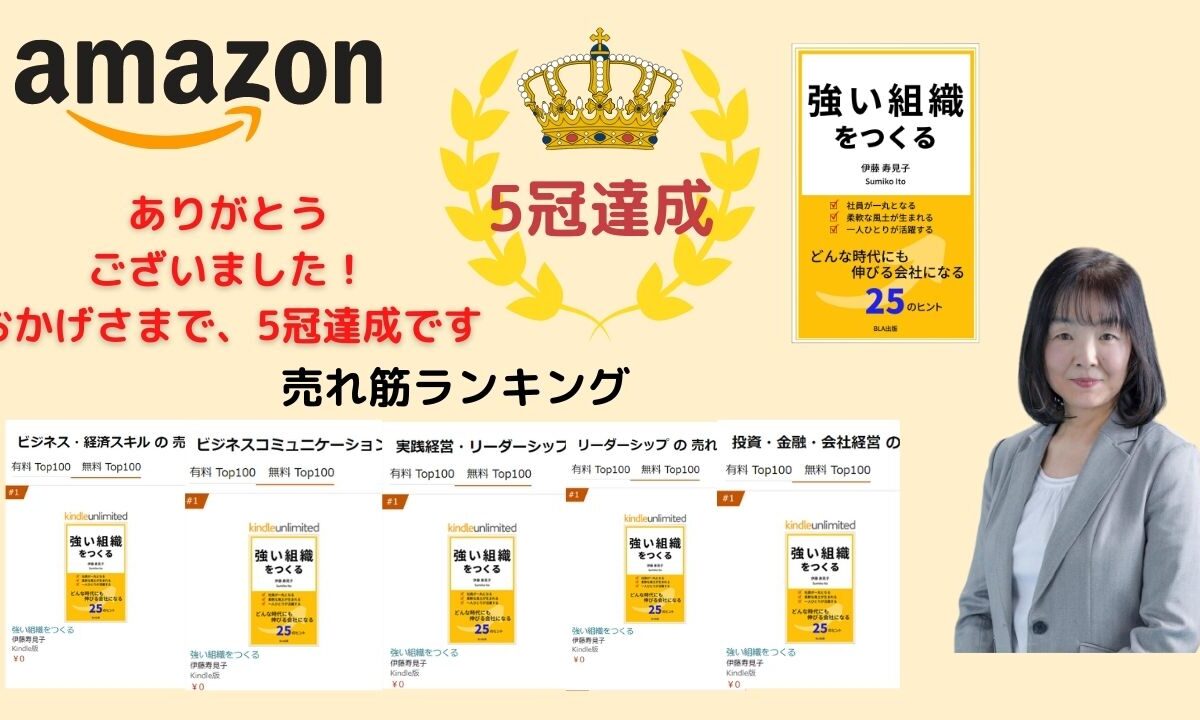
2022/11/7
傾聴でより良い人間関係を築き、人生を豊かにしよう!
強い組織をつくる 実践25のヒント便り
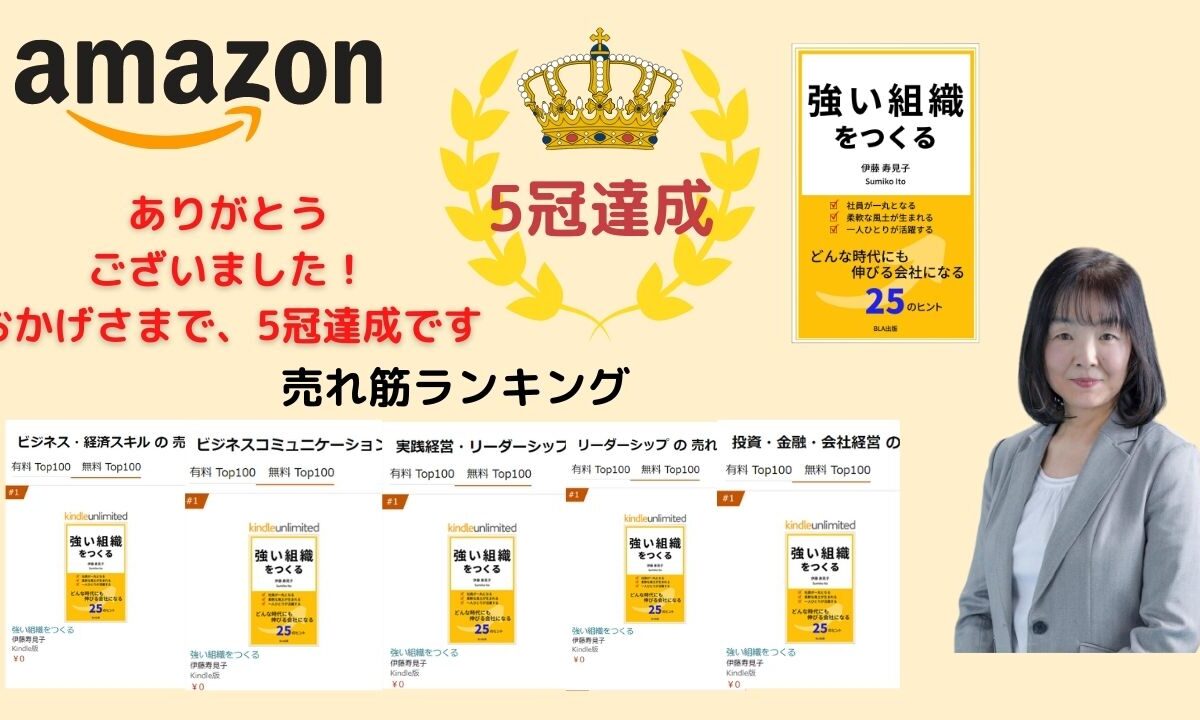
2022/10/31
上司が傾聴することで、部下が育つ!
強い組織をつくる 実践25のヒント便り
