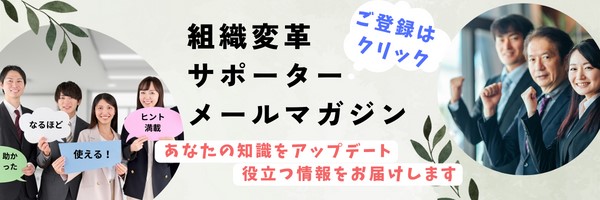「近頃の若い者は…」と嘆く年長者。
これはいつの時代にも見られることのようです。
ですが、近年の働き方の意識についてこれほど世代間でギャップを感じることはなかったように思いますね。
各世代の時代は、概ねこんな感じのようです。
- X世代:1960年から1974年生まれ
- Y世代:1975年から1990年代前半生まれ
- ミレニアル世代:1983年~1995年頃に生まれ
- Z世代:1990年代後半から2000年代に生まれ
- α世代:2013年から2020年中頃までに生まれ
皆さまは、どの世代ですか?
X世代からすると、結構ギャップを感じることあります。
今回は、これからの時代を支える中心となっていくZ世代を理解することから始め今後の組織の在り方を探ってみたいと思います。
本日のテーマ
Z世代と共創必須の時代に!
WBSという番組では、毎週金曜日にZ世代の特集があって楽しく拝見しています。
若い方々の活躍には目を見張るものがあります。
では、まず最初にZ世代の傾向を見ていきましょう。
- デジタルネイティブ
- ネットリテラシーの高さ
- 個々人の多様性の尊重
- 最新テクノロジーへの高い興味関心
- 経済感覚的にはコスパ(費用対効果)とタイパ(時間的効果)が気になる
- 仕事で自分が成長できるかについて敏感
- 自分らしさを大切にしている
- 消費に消極的と評されることもあるけれど、
自身にとって必要と考えるモノや体験には支出を惜しまない - ワークライフバランスを重視
- 社会貢献、社会課題の解決につながるような働き方を求める
- 理不尽な命令や、理由がクリアではない評価には納得しない
あるある、と思われたところも多いのではないでしょうか。
やる気を感じない部下に
「ビトンの鞄とか、欲しくないの!」
「いい車に乗りたいと思わないの!」
と、言ったところで、暖簾に腕押しです。
ブランド物に踊らされることがありません。
なので、バブルを謳歌してきたX世代の管理職の方の中には若手の働く意欲を引き出す方法が分からない、とおっしゃる方もいます。
随分、価値観が違うんですよね。
生まれ育った時代背景を理解することは大事です。
「今の若い者は!」と、嘆いているだけでは前に進みません。
俺の背中を見て育て、など昭和の当たり前は通用しません。
そんな上司のことを育成を怠けているように感じる若手もいます。
転職が当たり前の時代
どうすれば!
転職が常態化してきました。
手塩にかけて育てた社員に辞められるのは辛いですよね。
ですが、ここは「辞められるとつらい」という発想からさらにいい社員を採用できるかもしれないチャンスと、気持ちを切り替えてみませんか。
つまり、Z世代の傾向にみられるように
- 社会に貢献する企業
- 多様性を尊重する組織風土
- 社員が成長できる仕組み
- ワークライフバランス
これらが実現できれば離職率の低下だけでなく、さらに優秀な人財を採用することが可能になるかもしれないのです。
組織の在り方を見直す必要に迫られているとも言えますね。
年功序列の既存システムからの転換、合理性があり誰もが納得のいく人事制度の構築が求められます。
組織に足りない面を補うために、優秀なZ世代を採用し、デジタルネイティブ世代が持つ グローバル感覚やITリテラシー、そして最新テクノロジーの導入によって、組織が変革のチャンスをつかむことができるかもしれません。
これからの時代は
世代間ギャップを超えて組織を活性化!
今の日本は未知のゾーンに入りつつあります。
- 地政学リスクへの緊張感
- ChatGPTなどを始めとする生成AI技術の席巻
- 40年ぶりの物価の上昇
- 異常気象、気候変動の影響
などなど
この危機を乗り越えていくには世代間のギャップを超えて互いの得意なことをかけ合わせていくことが組織力強化の鍵になると思われます。
Z世代がいくらITリテラシーが高く、情報収集にたけていたとしても、正解をもっているわけではないです。
なので、年配社員の経験や知恵が必要となるでしょう。
と、ここで なんと偶然の出来事なのですが、すでに実践しておられる企業の記事を発見!!
ビックリしました。
某化粧品会社の取組みをご紹介しましょう。
(2023年9月15日 日本経済新聞から)
若手が幹部を指南
立場を超えて縦割り打破
「リバースメンタリング」
「リバースメンタリング」とは、若い世代が年配者の先生役になるという制度でいわゆる「メンター制度」の逆です。
この会社では、若手社員が幹部に先端のデジタル技術や消費トレンドを教え新規事業も議論する。
組織の垣根を超え、異世代での立場を逆転させた交流の場をつくっています。
変化の激しい時代にイノベーションの土壌をつくり、若手のキャリア形成の意識を高める効果も生んでいるようです。
所属や階層の壁を取り払った絆を増やす。
オープンでフラットな対話の場だからこそ双方が視野を広げて成長できるとのこと。
若手が新規事業を計画する時には、ペアーである部長からの経験に基づいたアドバイスを参考にして練り上げる。
若手からすると、自分と同じ目線に降りてきてくれた部長が自分の目指すロールモデルになったそうです。
もちろん、課題はあります。
若手はどうしても年配の社員には遠慮しがちになるし、年配の社員は、若手の話に謙虚に耳を傾け、若手の知見や発想を引き出すスキルも問われる。
ですが、このような取組みを参考にしてフランクに意見が言える組織をつくっていくことがこれからの時代に立ち向かっていく力になりそうですね。
この化粧品会社のように組織の絆を強めていきたいものです。
実現のためには
世代を超えて互いに尊重するマインド
これが最も大切なことと思います。
今日は、異なる世代の方と対話する時間を作ってみませんか!
それでは
今日も、ワクワク
楽しい1日をおすごしくださいね!!
最後までお読みいただき
ありがとうございました♪